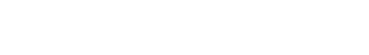DTMの総合情報サイト
DTMの総合情報サイト
 WAVES H-Comp
WAVES H-Comp
コンプレッサーはDAWレコーディング/ミックスダウン作業にはかかせないエフェクトです。小さい音はそのままに大きい音を圧縮する効果を持ち、楽曲の音量を安定させるために使用します。ボーカルやギター・ベースの音圧を安定させ、バスドラムやスネアなどパワー感が欲しい時にも使用されます。録音時・ミックスダウン・マスタリングと、どの工程でもお世話になるため、使い方はしっかりと覚えておきたいところです。それではコンプレッサーの使い方を見ていきましょう。
まずはコンプレッサーの役割について。
通常、コンプレッサーの利用法として真っ先に思いつく役割がこれです。音量のばらつきが大きいトラックのピーク部分のみを抑え込んで、全体の音量を均します。ピークを抑える必要があるため、アタックは速め、リリースは余韻に応じて適宜設定します。ベースやアコースティックギター、ボーカルなど、音量差が大きく、かつ一定の音量で安定させて聴かせたい楽器には特に重要な使い方です。ただし、ボーカルやヴァイオリン、管楽器でのメロディなどは、あまり音量差を無くしてしまうとダイナミクスが感じられなくなり、情感に欠けたメロディラインになってしまいます。特にかけ過ぎに注意しましょう。
アタック音を大きくし、鋭い音を作り出します。先述した通り、アタック遅めの設定を使い、ピークを過ぎてから一気に圧縮を掛けることでアタックのみを目立たせます。リリースはあまり長くし過ぎると、次の音の発音タイミングに掛かってしまうため、全体をよく聴きながら設定する必要があります。打楽器に特に有効で、スネアなどはこの設定次第で非常に強い存在感を演出できます。
アタックをつぶした上で全体の音量を上げることで、減衰音も一緒に大きくなり、相対的に音が伸びているように聞こえさせます。アタック速め、リリース速めの設定が基本。他の使い方に比べてあまり登場頻度は高くありませんが、ピアノや歪んでいないギターなど、音がすぐ減衰する楽器では効果的に使えるシーンが見つかるでしょう。ちなみに、ギター用コンプレッションサスティナーのエフェクターはこれを応用したものです。
ピークを含んだ全体を抑え込んで、上部に余白を作り、その分の音量を上げることで、全体の音量を一段階上に持ち上げます。個々の楽器でもドラムバス、ボーカルなどにはよく使われる手法ですが、特に最終ミックス段階においては、ほぼ必須と言って良い作業です。あくまで元の音色を壊さずに行うのが基本なため、レシオは2:1以下の小さな値にしておくことが普通。ヴィンテージ系のコンプレッサーは、程よいアナログ感や若干の歪みをもたらすことで楽曲をドライブさせられるため、この用途には好んで使われます。
ヴィンテージ系のコンプレッサーに多い特徴として、通すだけで音が良くなる、と言うものがありますが、これはその機材の持つ特有の回路を通すことで、若干の歪み成分が付加されるために起こります。歪み成分が付加されると倍音が豊かになり、中域がリッチになったり、音ヌケが良くなったり、様々な恩恵が受けられます。圧縮そのものに加えて、そのような効果を狙ってヴィンテージ系コンプレッサーが選ばれることは少なくなく、特に目立たせたいトラックに使うと効果的です。
 Logic Pro Xに標準搭載されているコンプレッサー・プラグイン。中央のメーターが反応することでコンプレッションのかかり具合が確認できる
Logic Pro Xに標準搭載されているコンプレッサー・プラグイン。中央のメーターが反応することでコンプレッションのかかり具合が確認できる
コンプレッサーには以下のパラメータが用意されています。
1.ゲイン(Gain):全体の音量レベルを調整する値
2.スレッショルド(threshold):コンプの効き具合の調整をおこなう値
3.レシオ(ratio):圧縮比率の値
4.アタック(Attack):スレッショルド値を超えてから圧縮するまでの時間
5.リリース(release):スレッショルドを下回ってから、コンプを解除するまでの時間
6.ゲインリダクション(Gain Reduction):圧縮した(減音した)音の大きさ

ゲインは文字通りオーディオファイルの出力レベルを調整する値です。コンプレッサーによって圧縮されると音量レベルが下がるため、それを取り戻すために使います。
例えば、スレッショルドを下げてゲインリダクションが-4dBと表示された場合、その時点で-4dB分の音量レベルが失われていることになります。そのため、ゲインを-4dB分上げて±0の状態に持っていく訳です。
もちろんやり方は様々ですが、「ゲインリダクションと同じ分だけゲインを上げる」と覚えておくと良いでしょう。ダイナミクス重視のミックスにしたい場合、ゲインリダクションの数値から-0.5dBあるいは-1dB引いた値に設定するのがオススメです。あえてピークまで余裕を持たせることで、ナチュラルな仕上がりになります。
コンプレッサーの効き具合を調整する値です。この値を下げることでオーディオファイルを圧縮し、ゲインリダクションの数値が上がっていきます。仮にあるパートを-8dBまで圧縮したい場合、ゲインリダクションが-8dBに達するまでスレッショルドを下げれば良いということになります。ゲインリダクションの値見ながら少しづつ下げていくのがコツです。
圧縮比率を表す値であり、割合が大きければ大きいほど「使用するコンプレッサーの特性が乗った圧縮感のある」になります。ボーカルやストリングス、ピアノなどのダイナミクスを活かしたいパートは1:2~1:4、キックやベースなどの太さが求められるパートは1:4~1:8あたりがオススメです。エレクトロ系の楽曲の場合はより大きな値に設定しても良いでしょう。
スレッショルドで設定した値を超えた後、音の圧縮が開始されるまでの猶予時間です。遅くすると圧縮が開始されるのが遅れ、結果的にアタック音が鋭角的になります。速くすると、ピークを超えてすぐに圧縮が始まり、アタック感がなくなります。なだらかな傾斜を保つため、なめらかな印象が強くなります。
圧縮された音が減衰し、やがてスレッショルドを下回った際にどのぐらいの猶予時間をもって圧縮を解除するかの値です。長いとスレッショルドを下回ってもなお圧縮が続き、短いと下回ってすぐに解除されます。長い方がコンプレッサーの効果が持続する、という感覚で概ね間違いありません。アタックとリリースは繊細な調整によって音のダイナミクスを大きく変化させられます。リリースにはオート機能が付いている場合があり、わかりにくい場合はそれに頼っても良いでしょう。
コンプレッサーが圧縮した量(dB)を表す値です。この値が大きければ大きいほど音が圧縮されていることになります。
ヴィンテージ系のコンプレッサーなどでは上で表記したパラメータが付いていないものも多くあります。特にスレッショルドが無いものは多く、そのようなモデルでは代わりにインプットやゲインが存在します。入力量を大きくすると、その分コンプレッションも大きく掛かっていくという仕組みです。アタックやリリースもデジタルほど細かく設定はできず、レシオは1:2、1:4、1:8などあらかじめ決まっており、そこから選ぶというものが一般的です。
スレッショルドを超えた音量をどれぐらいの比率(レシオ)で圧縮するかが、コンプレッサーの動作の基本です。レシオは高いほど音量が揃いますが、あまり強く掛けるとダイナミクスの幅が希薄になってしまいます。また、圧縮をし過ぎると最悪音が歪み出しますので、かけ過ぎには注意しましょう。また、アタックとリリースの値は、コンプレッサーの使い方においての最大のポイントです。以下の設定などはよく使われる上、コンプレッサーの動作を理解するのに適しています。いまいちコンプがわからない、という方はこの辺りからイメージしておくと良いでしょう。

圧縮開始が遅くなり、アタック成分がそのまま残ります。音量のピーク辺りで急に圧縮が開始され、そのまま音の減衰終わり近くまで圧縮され続けます。急峻なアタック音が得られるため鋭角的なサウンドになり、音の輪郭がくっきりします。打楽器などによく使われる設定です。音が前へ出てくるため、場合によってはボーカルなど、メインのトラックに使用しても良いでしょう。

スレッショルドを超えてすぐに圧縮が開始され、下回ると程なくして解除されます。音の輪郭がつぶれ、なだらかなカーブを描くことで、音全体がふわりとしたイメージになります。ストリングスなどアタックの乏しいソースや、極端な音量差を避けたいアコースティックギターなどにもよく使用される設定です。音が奥まって聞こえるため、ボーカルを邪魔するソースのアタックをこれでつぶしておくというのもよく取られる手法です。
また、このままゲインを上げると全体の音量アップに繋がるため、単純に音圧を稼ぎたい時にもよく使われます。この場合、特にレシオを高めにすると効果が強く、ボーカルなど音量がふらついて前へと出てこない場合に、4:1以上などの高めのレシオで掛けてやると、ぐっと前へ出てくる効果を実感できます。
 WAVES L1 Ultramaximizer
WAVES L1 Ultramaximizer
基本的にコンプレッサーと同じ動作原理ですが、アタックがほぼゼロであるのと、レシオが∞:1になっているものを、特別にリミッターと呼んで区別します。リミッターはスレッショルドを超えたものを一切通さない、門のような働きをするため、レベルオーバーでのクリップを防ぎつつ、音量をしっかりと確保したい場合に使用されます。コンプレッサーでもアタックを最短、レシオを最大まで上げて使うと、似た効果を得ることができます。
 Logic Proのマルチバンドコンプレッサー「Multipressor」
Logic Proのマルチバンドコンプレッサー「Multipressor」
マスタリングで使用されるのが楽曲全体に適用するコンプレッサー、マルチバンドコンプレッサー(通称:マルチプレッサー)。周波帯域を区切って、各帯域毎にコンプをかけることができるプラグイン。単一の楽器で使われることは少なく、ドラム全体をまとめたドラムバストラックや、楽曲の最終調整で使用されることがほとんどです。マスタリングでは主に低域を強めに、高域をわずかに圧縮してゲインを上げることで、安定した重低音と煌びやかさを得るような設定がよく使われます。
トランジェント・シェイパーは、コンプレッサーを使ってのサウンドデザインをワンタッチで行える、便利なエフェクトです。アタックとリリース、そしてレシオの値を複雑にイメージしつつ作り上げる”鋭角的な音”や”なだらかなサウンド”を、分かりやすいコントロール一つで瞬時に作り出すことができます。特にドラムなどの打楽器では効果絶大で、コンプレッサーと悪戦苦闘するよりも、簡単により良い効果を得られることもあります。コンプレッサーやリミッターに比べても後発品ですが、昨今急速にメジャーな存在となりつつあり、市販のプラグインも増えてきています。
ハードウェアのコンプレッサーには様々な動作タイプがあり、ソフトウェア・プラグインもこれらをモデリングしたものです。動作タイプ毎にどのような特徴があり、どうやって使い分けるかを紹介します。
 MANLEY Stereo Variable-MU
MANLEY Stereo Variable-MU
1950年代から使われている真空管回路を用いたコンプレッサーのことです。掛けるだけで楽曲に自然な暖かみを加え、ナチュラルに音圧を増幅させることができます。ハードウェアでは業界標準のマスタリング・コンプレッサー MANLEY Stereo Variable-MU などが有名。
真空管コンプレッサーは他の動作原理とは異なる独特の倍音付加効果があり、ボーカルトラックにインサートするとクリーミーなサウンドに仕上がります。70年代の洋楽で耳にする暖かみのあるサウンドはヴィンテージライクな楽曲と相性抜群です。音がグッと前に出てくる印象もあるので、ボーカルには光学式のコンプレッサーを使用するのが定石ですが、あえて真空管コンプをインサートするのも面白いでしょう。
真空管コンプレッサーを強めに掛けることで荒々しいサウンドに仕上げることができます。往年の名曲で耳にするドライブ感とパンチ感を持ち合わせたあのサウンドは真空管コンプによって作られていると言っても過言ではありません。
 TUBE-TECH CL 1B
TUBE-TECH CL 1B
Opto(=光学式)はLEDとフォトセルを組み合わせて動作するタイプのコンプレッサー。入力された信号(電流)がLEDを光らせ、フォトセルが光りの大きさによって新たに信号を送ることでコンプレッションされます。
反応速度が遅くぬるっとした掛かり方が特徴で、主にボーカルにトラックで使用されるコンプレッサーです。いわゆるコンプ臭さと呼ばれるものが限りなく少なく、それでいて波形はしっかり揃っているのが魅力と言えるでしょう。バラードやジャズなど、ダイナミクスを活かすボーカルトラックで使用することをオススメします。
光学式コンプレッサーはベースとの相性も抜群です。波形をパンパンに詰めたロックベースのようなサウンドには向いていませんが、低音感をキープしつつダイナミクスも感じさせるウッドベースなどに使用すると良い結果になることが多いです。強くリダクションさせて軽く歪ませるのも良いでしょう。
アコースティックギターのアルペジオはダイナミクスを重視するパートです。ダイナミクスを残したまま音の粒を揃えることが出来る光学式コンプレッサーはとても相性が良く、通すことで生々しく艶のあるサウンドに仕上げることができます。
 UREI 1176
UREI 1176
ハードウェア・コンプの名機 UREI 1176 に代表される FET は、1960年代後半のロックサウンドを作り出してきたといっても過言ではないコンプレッサーです。他の動作原理に比べアタック/リリースを速く設定できることからエッジの効いたソリッドな質感を出すことができます。
ロックサウンドなどダイナミクスよりも存在感を重視したいボーカルに掛けると良いでしょう。パワフルなドラムやディストーションギターに負けず、存在感をキープしたまま抜けの良いボーカルにすることが可能です。
音抜けの良いスナッピーなスネアドラムを目指す場合、FETのコンプレッサーがオススメです。設定次第でパツンとしてコンプ感満載のサウンドに仕上げることもできます。昨今のロックサウンドのスネアドラムにFETのコンプレッサーは欠かせません。
アタック/リリースをそれぞれ最速に設定することで独特の歪みを生み出すことができます。サチュレーターで作り出す歪みとは一味違い、パワフルでアナログ感のあるサウンドに仕上げることが可能です。
 Vertigo VSC-2
Vertigo VSC-2
1970年代に登場した、クリーンで味付けの少ない音色が特徴のコンプレッサーです。キビキビとした動作が特徴でレスポンスが速く素直な出音なので、あらゆるトラックに使用することができます。ただし、他の動作原理に比べ硬質なサウンドになりがちなので、ヴィンテージライクな楽曲で使用するには向いていないかもしれません。
光学式コンプレッサーほどぬるっとした掛かり方はしませんが、出音が素直な点、キビキビと動作する点を考慮するとボーカルトラックとの相性に優れていると言えます。そのため、光学式のコンプレッサーの代用にVCAを使うことができます。1つのトラックに2つのコンプレッサーをインサートするいわゆる二段がけを行うことで、よりナチュラルなサウンドに仕上がります。
VCAのコンプレッサ-はアコースティックギターやストリングスなど弦楽器との相性が抜群です。素直な出音なのはもちろんですが、設定次第で倍音豊かな煌びやかなサウンドに仕上げることが可能です。イコライジングしなくても抜けの良いサウンドになるため、音抜けが悪い時はあえてハイをブーストせずVCAのコンプレッサーを通して解決するのも良いでしょう。

プラグインの売れ筋を…
Aアマゾンで探す
Sサウンドハウスで探す
R楽天で探す
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。