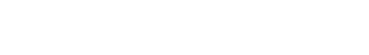DTMの総合情報サイト
DTMの総合情報サイト

Studio OneはWin、Mac両方に対応したDAWソフトウェア。2009年という大幅な後発にも関わらず、独自の強みを持つことで、多くのユーザーを獲得しており、Cubase同様に日本で特に人気のあるソフトです。
Studio Oneの初代バージョンは2009年、Presonusより発売されました。開発に当たってはかつてスタインバーグに勤めていた、ウルフガング・クンドラス、マシアス・ジュアンという二人が中心となって行われたため、Cubaseとの共通点、さらにそれをブラッシュアップしたような機能が見られることもあります。リリース当初から評価は高かったものの、バグなども多く、2年後の2011年には程なくメジャーアップデートが行われ、バージョン2がリリースされました。このバージョンからはピッチ補正ソフトとして有名なCelemony社のMelodyneが付随するようになり、これは本体ソフトに統合されることで、以後Studio Oneを代表する重要な機能となります。
それ以後もアップデートはかなり頻繁に行われ、2018年にはバージョン4、2022年にはバージョン5をリリース。低価格グレードであるStudio One Artistもこのバージョン5よりVSTに完全対応を成し遂げています。2023年夏現在、バージョン6が発表されたばかりで、今なお進化を続けています。
Studio Oneは独特の強みを多く持つDAWソフトです。下に述べる機能はほとんどがProfessional版のものを参考としています。
初期開発の段階で64ビットデジタルを前提としてソフト制作が行われたため、動作に無駄がなく、非常に機敏に動きます。また、インストゥルメントやエフェクトの読み込みをはじめ、多数の操作がドラッグ&ドロップのみで完結してしまうといった優秀な操作性を備え、DAWに不慣れな初心者でもとっつきやすいところは、シェアが継続して増えている一因ともなっています。作業ウインドウは一つにまとめられ、その中でMIDIトラックの編集、コンソール画面を用いてのミックスなども含めて行えるため、画面がウインドウで埋め尽くされることがなく、目線も迷わず、スムーズな作業が可能です。ソフトの挙動に関する部分はCubaseを制作する際のノウハウが参考にされており、初期バージョンから非常に高いパフォーマンスを発揮していました。
64ビットを前提とした無駄のない作りが理由か、Studio Oneはクリアで美しい音も特徴です。音抜けが非常に良く、各楽器を明瞭に聞き取ることができ、音質については最も高い評価を得ているDAWソフトと言ってよいでしょう。この部分は音楽において最も重要な要素であるため、これは他社製品からStudio Oneに乗り換えるケースの最大の要因ともなっています。
現在でも依然として一定数のニーズがあるCD用、アルバム用マスタリング。Studio Oneはマスタリングに特化した機能を別枠で持つ唯一のDAWソフトです。マスタリングは作業を行うためのソフトを別個立ち上げ、そこに完成済みの楽曲を並べていくのが普通ですが、このやり方は作業途中で単曲の中のバランス変更を行うのが非常に煩わしくなります。Studio Oneは同一のソフトの中にその機能を備えることで、単曲ごとにエクスポートをやり直す作業がほぼ必要なくなります。この機能はStudio Oneの初期バージョンの頃から存在し、同ソフトの強みとしてよく認知されています。
オーディオファイルからのコード検出機能や、コード入力を支援するコードトラック機能などは強力な作曲支援ツールです。専用のセレクターウインドウより選んでトラックに打ち込まれたコード進行は、メロディと合わせて楽曲のトラックと完全に連動します。コード進行を変えると、メロディやオーディオファイルまでがそのコード進行に合わせて自動で変化し、アレンジの調整などが非常に捗ります。前述した高い操作性とも相まって、制作の効率化を突き詰めたStudio Oneのあり方がよく現れています。
無料版として「Studio One Prime」が配布されています。バンドルソフトのように特定のハードウェアに付いてくるのではなく、普通に配布されているため、すぐにダウンロードして使えるフリーソフトとしての位置づけながら、機能は無料版とは思えないほどに充実しています。サードパーティ製のプラグインを追加することはできませんが、総合音源Presence XTにははじめから2GBのライブラリが付属し、エフェクトプラグインも10種類が使えます。トラック数も無限に増やすことができ、他社の体験版と比べてもずば抜けて高機能です。DAWにあまり詳しくない初心者からするとこの無料版で十二分であり、Studio Oneの裾野を増やすのに一役買っています。
またPresonus社は主に低価格帯でのオーディオインターフェースがラインナップとして充実していますが、いずれの製品を買っても、Studio One Artistが付属します。AIやLEなど、バンドル専門の廉価版を付属とするCubaseとはここも違いを感じるところです。
無料版のPrimeを除き、ArtistとProfessionalの2つのグレードがあります。オーディオI/Fなどハードウェア製品に付属するものはArtist版となりますが、これはPrimeをVSTに対応させたような立ち位置となっており、音楽制作をしっかりと行いたい場合はProfessionalの一択と考えるべきでしょう。
| Professional | Artist | |
| オーディオ、MIDIトラック数 | 無制限 | 無制限 |
| Melodyne編集 | ◯ | 体験版 |
| コード・トラック | ◯ | ✗ |
| オーディオ分解能 | 64bit | 32bit |
| 付属インストゥルメント数 | 5 | 5 |
| 付属エフェクト数 | 44 | 31(Ampireはベーシック版) |
| マスタリングスイート | ◯ | ✗ |
| 付属ライブラリやループ | 30GB以上 | 6GB以上 |
| 価格(2023年9月) | 52,800円 39,600円(Artistからのアップグレード) 39,600円(他社DAWソフトユーザ向け) |
13,200円 |
標準的なEQの使用法からダイナミックEQに至るまで、多彩な機能を持つ万能イコライザー。視認性の良いアナライザーが画面全体に広がり、操作性も良好です。DAW付属のEQとしてはかなりレベルの高いものになっており、使い込むことによってイコライザーを隅々まで理解できるでしょう。
Professional版に付属するコンボリューションリバーブ。得られる音の幅が非常に広く、通常のホールから、バーチャルで非現実的な空間まで様々な質感の残響を得られます。その分、操作は難しく設定も難しいですが、プリセットも充実しており、これ一つでリバーブはかなりの部分をカバーできるはずです。IRリバーブの特徴として、必要なマシンパワーが多いのは注意。
ギターアンプシミュレーター。特にクリーン~クランチのサウンドに強く、歪みの質感は付属ソフトの領域を越えてくるほど高品質です。キャビネット部分も複数のマイクをブレンドするなど、サードパーティ製の有料製品に勝るとも劣らないほど柔軟なセッティングが可能。ギターの音質にそこまで強いこだわりがなければ、これだけでも十分役割を果たせます。
本体に統合されたボーカルトラックの編集機能。バージョン2よりStudio Oneと連携しており、本体の機能の中において、シームレスかつ簡便な操作で編集できるようになっています。さすがにPro Toolsにも付属する業界標準のソフトだけあって、音質、編集機能は屈指のレベルに達しており、この機能をもってProfessional版を選択する価値があるほどです。
Presonusが生んだFETコンプレッサーの銘機RC500をモデリングしたもの。実機に忠実なモデリングが成され、アタックが速くパワフルで骨太なFETコンプレッサーの魅力を最大限に感じることのできるエフェクトです。インストール時には付属していないものの、アドオンとして後から無料で追加可能。
ピアノ、ギター、ドラムからサックス、バイオリンや民族楽器まであらゆる音色が出せる総合サンプラー音源。Professionalに付属するものではライブラリは15GB(Primeでは2GB)に上り、LogicのEXSやKontaktなど他社製のライブラリをインポートできるという機能を持っています。多数の楽器を一手に引き受ける、Studio Oneの中でも最大級に活躍する音源の一つです。
純正のドラム用サンプラー。初期の頃から付属しているものの、バージョンを追うごとにサンプラーとしての機能が見違えるほど充実し、現在では音色ごとにかなり手の込んだ編集、加工ができるようになり、優秀なサンプラーとして定着しています。ハードウェアも展開する会社だけあり、外部のMIDIコントローラーとの連携もスムーズで、多様な用途で活躍します。コアライブラリとして1.8GBのサンプルが付属し、Professionalではさらにアコースティックドラムのものを含めて1.5GB以上のライブラリが付属するので、種類を問わず総合ドラム音源として優秀です。

Studio Oneを…
Aアマゾンで探す
Sサウンドハウスで探す
R楽天で探す
YYahoo!ショッピングで探す
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz

dtm-hakase.biz